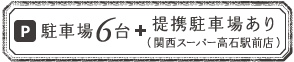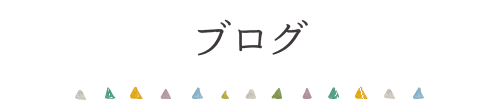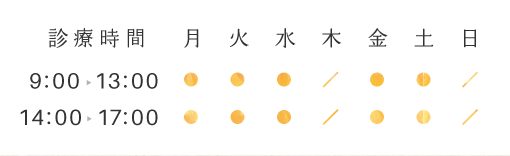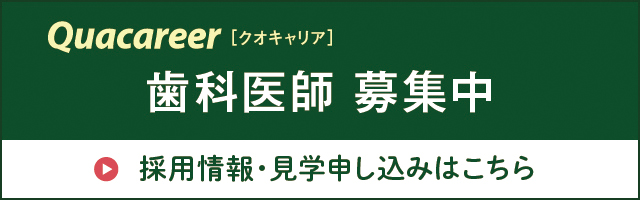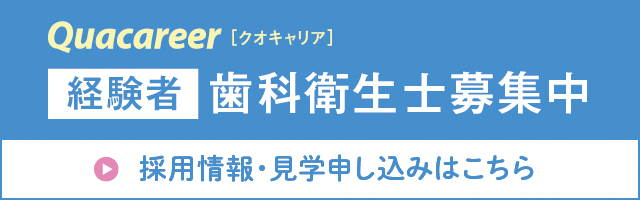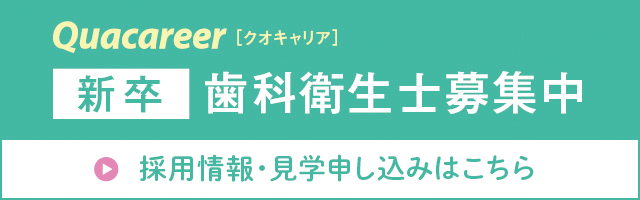遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。
なないろの森歯科クリニック 歯科衛生士の庄野です。
昨年は多くの患者様に来院いただき、感謝申し上げます。
2025年もみなさまに安心して通院していただけるよう努めてまいります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今回のブログのテーマは「カリオロジー」です。
カリオロジー?聞きなれない言葉ですよね。
カリオロジーとは、カリエス(むし歯)+オロジー(学問)の造語で、むし歯学という意味です。
むし歯の実体をきちんと把握してコントロールする学問です。
むし歯の原因について様々な研究が進み、以前は「むし歯はミュータンス菌と砂糖のせいで起こる」
とされていましたが、現在は「プラークを構成する細菌が(ミュータンス菌に限らない)、
発酵性炭水化物(砂糖に限らない)から酸を産生し、むし歯が起こる」と考え方が大きく変化しています。
今回は、みなさんのカリオロジーの常識を昭和から令和にアップデートしましょう。
Q1 歯ぐきを境に、歯ぐきより上と歯ぐきの溝の中の細菌の種類は同じ? ⇒×
A 歯ぐきより上はむし歯の原因菌が、歯ぐきの溝の中には歯周病の原因菌が住んでいる。
歯ぐきの中と外では住んでいる細菌の種類や好む環境やエサの種類が異なります。
歯周病の治療には、歯ぐきの溝の中のお掃除も必要になります。
Q2 むし歯の原因は砂糖だけ? ⇒×
A むし歯の原因は砂糖(ショ糖)だけではなく、発酵性糖質。
発酵性糖質とは、ショ糖、ブドウ糖、果糖、調理でんぷんなどです。
※調理でんぷん:熱と水分を加えて調理したでんぷん
つまり、甘いジュースやお菓子だけがむし歯の原因ではないということです。
Q3 むし歯原因菌には天敵の細菌がいる? ⇒〇
A むし歯原因菌に対して抗菌物質を出したり、むし歯原因菌が出す酸を中和したりする善玉菌が
存在します。このような善玉菌が多いプラークはむし歯を起こしにくいと言われています。
Q4 むし歯原因菌の母子伝播(母親から菌を獲得すること)は絶対に避けるべき? ⇒×
A それほど神経質にならなくてもよい。
以前は、むし歯原因菌は「感染の窓」と呼ばれる生後19ヶ月~31ヶ月の期間に両親から伝番すると
言われていました。虫歯予防のため、母子伝播を避ける方法として食器の共有やキスなどのスキンシッ
プも控えるべきといった考え方がありました。
現在は、両親以外からの伝播があることや、むし歯の原因菌がミュータンス菌だけではないことが分か
ったため、むし歯を発症させるすべての細菌種の伝番を防ぐのは難しいこと、そして伝播しても食事指
導やフッ化物の使用、適切なブラッシングで発症が予防できるため、それほど神経質になる必要はない
という考えが広まっています。
Q5 お口の中の細菌叢は常に一定? ⇒×
A 細菌の種類は変わらないが、菌量が増える細菌種と減る細菌種がいる。
いったん定着した細菌種はそう簡単には変わりません。しかし、菌量の比は頻繁に変化します。
たとえば食事によって口腔内が酸性に傾くと、酸性が好きな菌(悪玉菌)が増殖し、酸性に弱い菌(善玉菌)
が減少します。そのためプラークの酸性がさらに強まり、プラークの病原性が高まります。
Q6 むし歯は治る病気? ⇒×
A むし歯の原因菌は常在菌なので完治はない。
“削って詰める”治療によって、むし歯は“治る”と考えられていました。
昭和の歯科医院は、痛くなったら行くところでした。
しかし、削って詰めることは原因除去ではありません。むし歯の原因は酸を出す口腔常在菌です。
常在菌とは“常にいる菌”なので、口から追い出すことはできません。
虫歯治療とは、『むし歯ができる環境にならないように口腔内を管理すること』です。管理が不十分だ
と、むし歯は起こります。だから、むし歯に完治はないのです。
今回は、“令和”のカリオロジーの一部をご紹介させていただきました。
むし歯の原因などとネット検索すると、いまだに古い情報や誤った情報であふれています。
病気の予防と治療は、病気の原因を取り除くこと。
ですから、むし歯の予防と治療のためには、むし歯の原因を正しく理解する必要があります。
古い知識にとらわれず、常に新しい情報をアップデートし、正しい選択をすることであなたの大切な
お口と体の健康を守っていきましょう。
このブログでは、これからもみなさんのお役に立つ情報を発信していきますので、
今後もぜひご覧ください。
なないろの森歯科クリニック
歯科衛生士 庄野